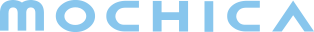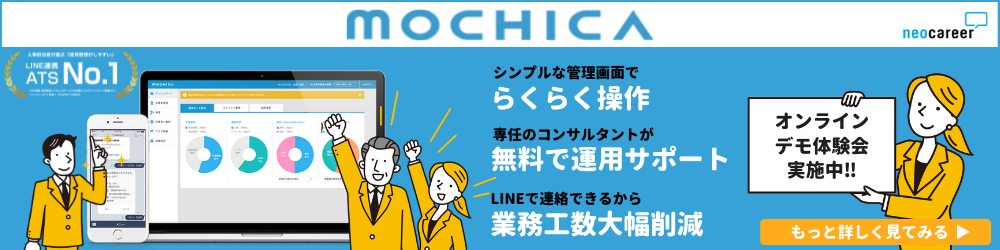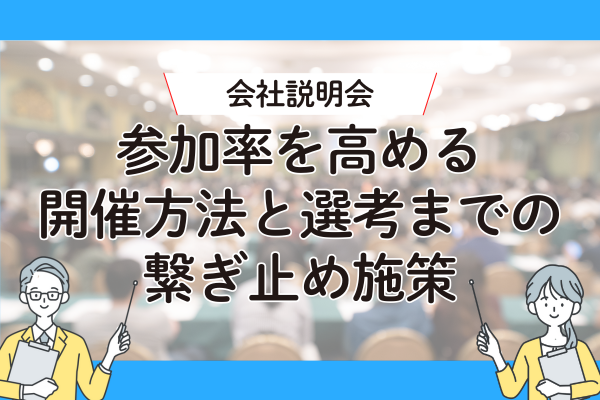
かつて「3月説明会解禁」「6月選考解禁」というルールが、学生と企業の動きを区切っていました。
しかし現在、そのスケジュールはほとんど形だけのものになっています。
実際、2026年卒の学生の多くは大学3年生の夏からすでにインターンシップに参加し、秋の時点で志望先候補を固め始めています。統計でも、解禁前にすでに学生の約半数が内定を保有しているというデータが示されており、従来の就活ルールに沿った対応では、優秀層との接点を逃すリスクが高まっています。
つまり今の採用市場は、公式スケジュールよりもはるかに早く動き出すことが前提。
「3月からで十分」という考え方は通用せず、学生のスピード感に合わせて企業も早期から関係を築くことが欠かせない時代になっているのです。
となると、複数企業から内々定を得る学生も出てくるわけですが、
優秀な学生を採用したい人事担当者様に求められるのが、まず「説明会予約〜当日までの繋ぎ止め」です。
自社を就職先として選んでもらうには、まず説明会に来ていただく必要があります。
「繋ぎ止め」と文章で書くのは簡単ですが、その実情は難しいもの。
なぜなら、「説明会、絶対に来てくださいね!」と熱意を伝えても、貴社を第2志望以下に考えている学生にとっては、
その熱烈なラブコールがプレッシャーになってしまい、彼(彼女)らが、来ないケースがあるからです。
予約をいただいても、説明会に来ない時点で、学生の頭の中から貴社は、「就職先の候補」から消されています。
そこで本記事では、具体的な手順を交えて「会社説明会の参加率を高める方法」について、まとめていきます。
この記事の目次
学生が説明会に求めているモノはなにか
いまの学生は、企業の基本情報をわざわざ説明会で聞かなくても、X(旧Twitter)やInstagram、TikTok、YouTube、
就活系アプリ、さらには各社の採用サイトから、簡単に手に入れることができます。
事業概要や数字情報といった“文字で伝えられること”は、
すでに学生の頭の中にインプットされている前提で動いているのです。
だからこそ、企業説明会で本当に価値が出るのは「ネットには載っていないこと」をどう伝えるか。
特に、学生が一番知りたいのは 「自分が入社したら、どんな仕事を任されるのか」 というリアルな部分です。
そこで効果を発揮するのが、入社3〜4年目の若手社員による座談会。
人事や役員の言葉よりも身近で信頼感があり、学生にとっては自分の将来像を描きやすい時間になります。
入社3年目〜4年目の社員様ならば、各部署の役割、人事異動の流れをおおむね把握しているでしょう。
正直なところ人事担当者が時間をかけて資料を作っても
「専門用語が多くてピンとこなかった…」と話す学生は少なくありません。
正社員という責任のあるポジションで働いた経験のない学生にとって専門用語は、
異国の地でアラビア語を聞かされているのと同じ感覚です。
そんな状況、私たち、ビジネスパーソンでも戸惑ってしまいますよね…。
学生はたとえ貴社が第一志望であっても「根本的に意味がわからない…」「これは質問して良いのか…?」と迷ったら、ほとんどの人が質問をしません。
なぜなら、質問した結果、人事担当者に「この人は分かってない…」とマイナスな印象を残したくないからです。
それゆえ「入社3〜4年目の社員様に協力してもらう」との方法が、分りやすく、有効と言えます。
説明会と座談会の開催方法
開催にあたり、座談会に参加する社員様に気をつけていただきたいのが「敬語を使いすぎないこと」です。
普段の業務では自然と敬語になりますが、説明会でも同じように丁寧すぎる言葉ばかり使ってしまうと、
学生も「自分もきちんとしなきゃ」と無意識に肩に力が入り、本音を話しづらくなってしまいます。
もちろん最初から砕けた口調で話す必要はありません。
ですが、学生が少しずつ慣れてきたら、「そうですね」を「そうだね」に変えるなど、
ほんの少しだけ言葉を柔らかくしていくと、学生も安心して会話に参加できるようになります。
説明会・座談会の進め方については以下の記事に詳しくまとめていますので、ぜひご一読ください。
▷選ばれるには「惹き付け」が必須!学生が魅力を感じる説明会の運営術
こうした“場の雰囲気づくり”は重要ですが、実はそれだけでは十分ではありません。
説明会や座談会でどれだけ良い印象を与えても、その後の連絡が途切れてしまえば、
学生の関心はすぐに他社へ移ってしまいます。
そこで大切なのが、開催後のフォローです。特にLINEのように学生が日常的に使うツールを活用し、
「今日は参加ありがとう!」と一言声をかけるだけでも、
学生にとっては「ちゃんと見てもらえている」という安心感につながります。
このように、開催方法とその後の連絡をセットで考えることが、選考までの“つなぎ止め”には欠かせません。
次の章では、具体的に「選考までのつなぎ止めを成功させる方法」について見ていきましょう。
採用管理システム導入は「繋ぎ止め」に影響するのか
「説明会には来てくれたのに、その後ぱったり連絡が途絶えてしまった」
「予約してくれた学生が当日来なかった」
採用担当者様なら、一度は経験のある光景ではないでしょうか。
この“繋ぎ止めの難しさ”こそが、今の採用現場で最も頭を悩ませるテーマです。
採用管理システムを導入すれば学生をつなぎ止められるのか?そう疑問に思う方も多いでしょう。
結論から言えば、「繋ぎ止め」は電話やメールでもできます。ですが、問題はそこではありません。
Excelで応募者情報を手作業で管理したり、経営陣が勝手に様式を変えてしまったり
そんな日々の雑務に追われていては、肝心の学生対応に時間を割けなくなるのです。
採用管理システムを導入する大きな価値は、工数を削減することで “学生と向き合う時間”を増やせること にあります。
MOCHICAをはじめ多くのシステムは権限設定がしっかりしており、無断で様式が変わる心配もありません。
これまで「事務作業」に奪われていた時間を、「学生の心を掴むためのコミュニケーション」に振り向けられるようになるのです。
一方、学生の行動も大きく変化しています。いまや企業研究の中心はInstagramやX(旧Twitter)、就活系アプリ。
説明会に参加する段階で、すでに企業情報を把握しているケースも少なくありません。
だからこそ重要なのは「参加後にどう繋ぎ止めるか」です。
ここで威力を発揮するのがLINE。学生が日常的に使うツールだからこそ、メッセージが埋もれにくく、
心理的な距離も近い。説明会後に「今日はありがとう!どう感じた?」と一言送るだけで、
学生は「自分を気にかけてもらえている」と感じ、他社との違いを実感します。
つまり、採用管理システムで事務作業を最小化し、
その浮いた時間をLINEでのフォローやSNSでの情報発信に投資する。
これが今の時代に合った“選考までのつなぎ止め”の最適解なのです。
MOCHICA運営部でも、導入企業様の声をインタビュー形式で紹介しています。
導入前後で「どれだけ学生との向き合い方が変わったのか」を知ることで、
より具体的にイメージしていただけるでしょう。
▷LINEで「安心感」のある内定者フォローを。学生の心をオンラインでも繋ぎとめる秘訣/ジャパニアス株式会社 様
▷内定数昨対450%!LINEを活用して歩留まり大幅改善/株式会社ヤスナ設計工房 様
MOCHICAと他社の採用管理システムの違い
最後に、弊社で提供しておりますMOCHICAの特徴と運用体制について紹介させてください。
1.学生の希望も考えたシステム
業務効率だけを考えれば、応募者全員に同じメッセージを送るのがもっとも効率的です。
ですが、裏を返せば1人ひとりの状況に応じた発信ができないため、
貴社を第2志望以下に入れている学生は「全員に同じメッセージを送っている」と感じとるものです。
インターンシップや会社説明会では「いっしょに働たい意思」を示しておきながら、内々定通知後に、そんなメッセージを送ってしまっては学生は「事務的にやっているだけ」と感じ、彼(彼女)らの志望度はあっという間にさがってしまいます。
これでは、信用を失うのは目にみえています。
貴社を「就職先」に選んでいただくには、上述のとおり、”学生1人ひとりの就活状況に応じたフォロー”が欠かせません。そこで、MOCHICAはそういった情報発信ができるよう設計。
MOCHICAの管理画面から、学生の選考状況をみた上で個別に情報発信していただけます。
このほか、採用管理システムといえばLINEをベースにしたものがほとんどですが、私たち運営部は「就職活動にLINEを使いたくない学生もいるだろう」と考えました。
そこで、MOCHICAでは学生1人ひとりの希望に応じて「メール」か「LINE」かを選べるようにしました。
これにより、いま学生とメールで連絡を取っている人事担当者様は違和感なく移行していただけると思います。
2.リッチメッセージの効果が分かる設計
くわえて、MOCHICAは「リッチメッセージの未読・既読」が管理画面で分かるようになっています。
たとえば、会社説明会の日程登録をリッチメッセージで送ったとき、
その既読率が高ければ、「学生の関心が高い」と評価できます。
ここで、リッチメッセージの効果を検証するときに必ずやっていただきたいのが、
「なぜそうなっているか」の分析です。
具体的に言えば、学生の中には貴社と他企業の日程が重なって、
どっちを優先しようか…と迷っている人がいないとも限りません。
あらゆる可能性を考えた上で、上記の場合は、人事担当者様から「日程変更、もしくは説明化について質問や不安点がある場合、いつでも連絡してくださいね!」と一報を入れてあげると親切です。
大学で「第一印象が合否を左右する」と口酸っぱく言われている学生は
『粗相があったら落とされる』と考え、彼(彼女)らの多くは質問しません。
リッチメッセージの効果可視化と分析により、先回りしたフォローが可能です。
企業様側が先にアプローチすると、学生は返答しやすくなり、より活発なコミュニケーションが見込めます。
3.「成果が出ない」を無くす運営体制
多くの人事担当者様も、プライベートでLINEを使ってらっしゃるでしょう。
しかしながら、パートナーや息子さん、娘さんと話すのとは勝手が違います。
なぜなら、学生は自分の家族ではないからです。
それゆえ「学生と距離感を縮めたいけど、どんな文章を送るのが最適か…」「絵文字は何個くらい使うべきか…」と悩むケースもあるかと思われます。学生の志望度がもっとも下がるのは、企業からの連絡が途絶えたときです。
MOCHICAでは契約成立時から、専任のスタッフが並走。貴社の採用課題や目標をお聞きした上で、学生1人ひとりの就活ペースに応じたメッセージの作成をサポートさせていただきます。
このため、人事担当者様がリソースを割けない場合でも、安定した運用が可能です。
※上述の分析作業なども、専任スタッフがサポートいたしますので、ご安心ください。
説明会後も「学生との接点」を継続するために
記事の序盤にも書きましたが、学生は同時期に複数の説明会に参加、選考を受けるのがスタンダードになっています。
人事担当者様からすれば、学生から積極的にアクションを起こして欲しいところですが、
彼(彼女)らの多くは、選考を見据え「わるい印象を残したくない」と考えているため、
学生からのアクションはないと思っていただいて構いません。
それゆえ、説明会終了後にメールでもLINEでも良いので連絡先を交換し、
人事担当者様側からアクションを起こせるかが、繋ぎ止めのカギになります。
連絡先を交換したあとに送るメッセージや、そのタイミングについては、
以下の記事にて紹介していますのでご一読ください。
▷【採用プロセス別】LINE例文。インターン募集、内定者フォローなど
まとめ
学生は限られた期間の中で「自分がやりたい仕事」「自分ができる仕事」をそれぞれ考え、就職先を決めます。
彼(彼女)には、中途採用者のように社内の責任あるポジションで働いた経験がありません。
それゆえ、「自分にとって“適職”とは何か」「今の自分に何ができるのか」を悩むのです。
その第一関門が、説明会予約から参加までのあいだになります。
正直なところ、自分に何ができるか分からないからこそ、軸を決めないまま、
とりあえず説明会に申し込んでいる学生も見受けられます。
本来なら、就職活動において軸作りは「学生の仕事」ではありますが、
売り手市場であるがゆえに、軸を絞りきれない人も少なくないのが実情です。
こうした実情を踏まえると、人事担当者様におかれましては、単なる「説明」ではないですが説明会。つまり、学生と貴社の社員様がしっかりコミニュケーションを取れる機会が求められるようになっていると言って良いでしょう。
その施策の1つとして説明会と座談会の同時開催が参加率アップには不可欠です。
かつ、「終わったら選考まで放置」ではなく、連絡先を交換したあとのやりとりが繋ぎ止めに必要となります。
だからこそ私たち運営部は、事務作業に係る工数を減らし、人事担当者様が
学生1人ひとりとのコミュニケーションに時間を割けるよう、MOCHICAを開発しました。
ひとくちに「就活生」と言っても貴社への志望度や、貴社を応募した経緯は人によりさまざまです。
繋ぎ止めを目的にメッセージを書いても、「本当にこれで効果が出るのか…」と迷うケースもあるかと思われます。
記事中において触れましたが、MOCHICAではご契約後、商社や大手メーカーで人事業務をになった社員が、
「専任スタッフ」として貴社の採用成功まで並走いたします。
MOCHICAの費用や具体的なサポート体制については、以下をご覧ください。
「MOCHICA」に関する資料を無料配布中
学生に入社していただくために、採用担当者は学生にとって、不安を打ち明けやすい人になる必要があります。
企業への連絡の際、「粗相があったら、印象を損ねてしまう」と考える学生は少なくありません。
学生と良い関係を築くには、第一に「コミュニケーションのハードルを下げる」必要があります。
採用活動はメールや電話のみでも展開できますが、学生の利用率が高いLINEで日頃からコミュニケーションを取った方が、学生1人ひとりと良い関係を構築しやすくなります。
MOCHICAは、「企業様と学生を”も”っと、”ちか”くに」をコンセプト展開する採用管理システムです。
下記フォームから、「MOCHICAのサービス内容」や「サポート体制」をまとめた資料を、無料でダウンロードいただけます。LINEの導入を検討されている企業様や、学生とのコミュニケーションに課題を感じている企業様は是非お申し込みください。
以下の資料をご覧いただけます