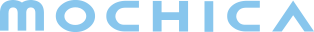最終更新日 2025年5月23日
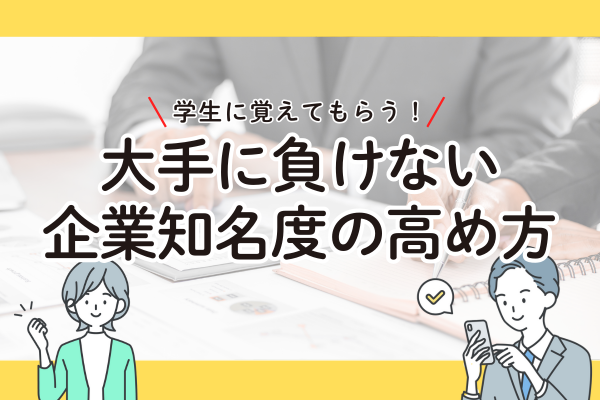
売り手市場、そして採用の早期化が進むいま。
採用成功の第一関門は「母集団形成」です。その鍵を握るのが、「学生に知ってもらうこと」。まずは、貴社の存在を認識してもらうことがスタートラインになります。きっと、X(旧Twitter)やInstagramなどで情報発信をしている企業も多いと思います。
ただ、注意したいのは、学生の多くは就業経験がないということ。
そのため、BtoB企業や地方企業についての知識やイメージがなく、情報も届きづらい傾向があります。このような背景から、採用活動の序盤はどうしても「大手企業に人が集まりやすい」という現象が起きがちです。
だからこそ、いま求められているのは「知名度をどうやってつくるか」という視点。
今回は、学生に“知ってもらう”ための採用戦略について解説していきます。
そんな実情を背景に、「TwitterやInstagramをやっているけど、学生から想定していた反応が得られない…」「大手に負けている感じがする…」といった課題をかかえていらっしゃる人事担当者様は少なくないでしょう。
本記事では、そのような人事担当者様に向けて「大手に負けない企業知名度の高め方」をまとめていきます。
この記事の目次
知名度を高めるには”らしさ”が不可欠
率直に申し上げて貴社が大手企業に勝つには、学生が「おもしろい」と感じる動画を作るのがもっとも有効です。
が、それを目指して社内で出来うる限りの施策をやっても「学生から反応がない」というのが実情かと思われます。
その理由は志望度の高い学生を集めることだけにフォーカスしているからです。
採用の成功を目指す以上、志望度の高い学生を集めた後と考えるのは当然と言えます。
そこで多くの人事担当者様が、実務のイメージを伝えようと、仕事風景や若手社員のインタビューをされると思います。
そのような施策も有効ではありますが、すでに多くの企業様が実施してるため、これだけでは同業他社との差別化ができず、学生の目に留まらないのです。
知名度の向上≠母集団形成
そのような現状の打開策として、私たちMOCHICA運営スタッフは、
人事担当者様に対し、「知名度の向上」と「応募者の募集(母集団形成)」は分けて考えるべきだとお伝えしています。
そもそも、この2つは目指すゴールが異なります。
- 知名度向上は、「多くの学生に企業を知ってもらうこと」
- 母集団形成は、「実際にエントリーやイベントに参加してもらうこと」
知名度が上がったからといって、必ず応募が増えるとは限りません。数字で追うのも難しいです。でも、学生が「この会社、なんか気になる」と思うことで、後々の応募や内定後の離脱防止にもつながります。つまり、知名度向上は長期的な採用課題の解決につながる土台づくりなのです。そして今の学生は、「雰囲気の良さ」や「安心して働けるか」を重視しています。
「うちはフラットで仲がいい職場です」と言っても、正直そこまで響きません。
なぜなら、その言葉が“キレイすぎる”からです。
学生は「パワハラはないか?」「休みづらくないか?」など、リアルな働き方を気にしています。
だからこそ、文章で伝えるより、動画で“見せる”ことが効果的です。
- TikTok・YouTube:職場の雰囲気や人間関係をそのまま伝える
- Instagram:社員のリアルな声をインタビューで届ける(なぜこの会社を選んだか、など)
このように、「知名度を上げる施策」と「志望度の高い学生を集める施策」を分けて設計することで、より多くの学生に“刺さる採用広報”が可能になります。
知名度を高めるための施策
採用目標を達成するには、学生に貴社の存在を知っていただかなければなりません。
そのために有効なのが「テンポの良さ」です。
1.再生されやすい動画とは
学生が貴社の動画を最後まで見るのは、貴社の投稿を「おもしろい」と感じたときです。
情報収集の時点では、長い動画よりも1分〜2分の短い動画のほうが、離脱されない傾向がみられます。
このため、「知名度を高める施策」においては短い動画が有効です。
BGMはゆっくりしたものよりも、少し速いものを使うと、動画のテンポもよくみえます。
これに加えて、使うBGMを決めておくと貴社が投稿を繰り返すたびに、学生は「あの会社の動画だ」と思うようになり、彼(彼女)らに覚えてもらいやすくなります。
2.コンテンツの考え方
学生は大学などでの就活セミナーでビジネスマナーを学んでいるため、「就職活動=失礼やちょっとしたヘマも許されない」と考えています。
そうした学生の認識もあり、TikTok・YouTubeでは「会社で料理してみた」「若手社員が社長にタメぐち使ってみた」といった就職活動のタブーに触れる動画が再生されやすくなっています。
ですが、率直に言って今から貴社がそういった動画を作るのはおすすめできません。
なぜなら、そのような動画で知名度を高めている会社がすでにあるからです。
そんな中、同じような動画を作っても学生に「二番煎じ…」と思われるのが関の山。
戦略を練り時間をかけて動画を作っても、内容が他社と似ていたら、学生に良い印象は残りません。
私たちMOCHICA運営部は良い印象を残すために、人事担当者様に対し「サクッと観られる動画を作り続けるべき」とお伝えしています。
より正確に言えば、目立つことだけを考えれば、就職活動のタブーに触れる動画を作るのも戦略として有効です。
しかし、「営業」、「企画」、「採用」など貴社の中で役割が明確になってから上述のような動画を作ると、組織として統制が取れず炎上してしまうケースが見受けられます。
実際のところ、「会社が成長し、規模が大きくなると統制面で訴求しづらい」と話す人事担当者様は少なくありません。
社内で統制がとれなければ、炎上し学生に貴社のイメージを誤解されてしまう可能性があります。
いっけん、地味に感じるかと思われますが、社内で分業できているならば、テンポを意識して「社員のスケジュール紹介」「オフィス紹介」といった動画をコツコツと作り続けたほうが、効果が見込めるのです。
3.施策の評価
TikTokやYouTubeの運用担当者様にとっては、すぐに結果が欲しいところでしょう。
インターネットの世界では、1つのコンテンツが爆発的にシェアされることがあります。
そのような波に乗れるのが理想的ですが、このようなケースは稀です。
動画を作りはじめたとき、反応はほとんどありません。
最初は心が折れそうになるかもしれませんが、続けているうちに「いいね」がついてきます。
少なくとも1ヵ月は最初の施策を継続。
1ヵ月経って平均20以上の「いいね」がついていない場合には、施策を見直しましょう。
応募者を集める施策
TikTok・YouTubeで平均20以上の「いいね」がついたら、応募者を集める施策に移ります。
1.投稿内容
TikTok、YouTubeで貴社に興味をもった学生が次に気になるのは、「自分にとって貴社が働きやすいか否か」です。
それを判断するために、学生はYouTubeの長い動画やInstagram、Twitterのアカウントを探します。
企業様側としては、働きやすさを伝えるため若手社員様へのインタビューをされると思われます。
コンテンツの考え方としては、間違いではないですが、単にインタビューをしても、それは学生にとって働きやすさを判断する材料になりません。
なぜなら、台本があり言わされているように見えてしまうからです。
(1)動画の場合
2010年代前半は就職活動の情報収集と言えばナビサイトと会社のホームページが中心でしたが、今はTikTokやYouTube、Instagramで簡単に情報を集められるようになりました。
ツールの増加に伴い、学生の情報収集力は年々あがっています。
そんな中、以前と同じ感覚で、貴社のアピールポイントだけを見せても、彼(彼女)らは「リアリティーがない……」と感じてしまうのです。
その打開策として、MOCHICA運営部では人事担当者様に「インタビュー動画を公開するなら、準備の様子もあえてカットせずに見せるのが良い」とお伝えしています。
準備はインタビューの本題に関係ないので、カットしがちですが、本番前の作り込んでいない部分にこそ、社員様同士の飾らない関係性が映るものです。
長く過ぎると学生が飽きて離脱してしまいますが、2分程度であれば流しても構いません。
(2)記事を書く場合
写真と文章でインタビューの様子をみせ、ナビサイトなどに掲載するときには、記事の冒頭でインタビュアーとインタビューイーの関係性が分かる紹介文を入れると、学生はスムーズに読み進められます。
インタビューは「出会いのきっかけはなんでしたっけ?」、「私の第一印象どうだった?」といった問いから始めると、違和感なく学生に社員様同士の関係性を伝えられます。
2.コンテンツの考え方
上述のとおり、学生が気になるのは「自分にとって貴社が働きやすいか否か」です。
コンテンツとしては、彼(彼女)らがそれを判断できるインタビュー動画、記事が良いでしょう。
このほか、貴社に興味をもった学生は選考の合格基準に関心を示します。
そこで、以下のように社員様が選考内容や対策ポイントを解説する投稿もおすすめです。