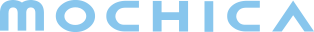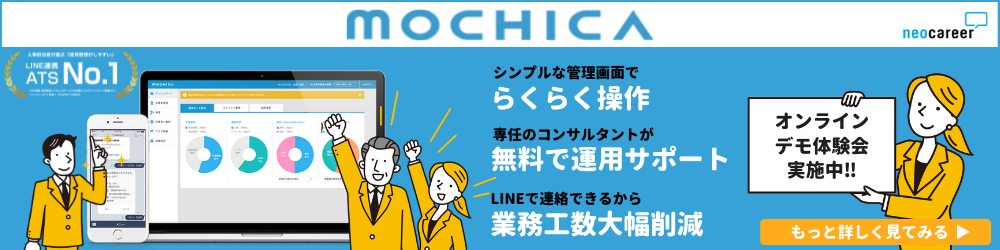最終更新日 2022年11月17日
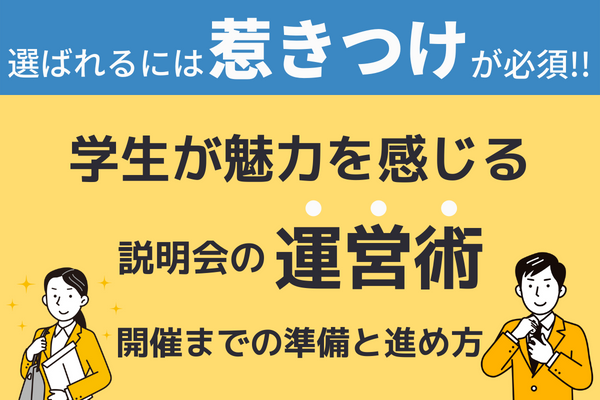
売り手市場で1人の学生が複数企業から内定を得るのがもう珍しくない今の時代。
説明会の瞬間から学生とどのように接点を持ち、何をして彼(彼女)らの気持ちを、自社に引っ張ってこれるか悩む人事担当者様は少なくないです。
採用活動を行う上で、学生と接点をもつタイミングはいくつかありますが、一番のポイントになるのが会社説明会です。以前だと3月1日に一気に解禁となった就職活動も、今は早期化によって決まった時期なく進めているのが現状です。学生は説明会及びインターンに参加して会社を見ています。掲載されている情報よりも自分たちが出会う情報によって判断を行う学生が年々増えている傾向です。
学生たちは、参加した説明会で得た情報を比較し、「自分に合う(文化や環境がいいと判断される)会社」かつ「自分が活躍できると思われる会社」を”第一志望”にしています。
採用業務を主導される人事担当者様の立場で言えば、「説明会をいかに競合他社と差別化できるか」。
その上で学生をどれだけ貴社に惹き付けられるか、彼(彼女)らが貴社の志望順位を何位に置くかが決まります。
本記事では「学生を惹き付ける会社説明会の開催方法」をまとめていきます。
この記事の目次
目立つ≠集まる
学生を集めるには、まず貴社を学生たちに認識してもらうことが大前提になります。
しかし今の就活市場では「知ってもらう」だけでは足りず、いかに自社の雰囲気や社員の人柄をリアルに伝えられるかが勝負となっています。
実際、大阪・難波のIT企業である株式会社ビヨンドがPCゲームマインクラフト内で、開催した会社説明会が、Twitter上で話題になり大きな注目を集めました。
その一方で、MOCHICAをご利用いただいている企業の人事担当者様と話をすると、「インターンシップでは学生の食いつきが良かったけど、説明会の感想を読むとイマイチだった…」と運営の難しさをくちにする担当者様は少なくありません。
今の学生は、ナビサイトやSNSなどで企業情報を簡単に調べられる時代。
「事業内容」や「会社概要」だけでは他社と差別化が難しく、最終的な判断材料は「社員の人柄」や「社内の雰囲気」に移っています。
だからこそ、人事担当者様の多くが「自社では、何を全面に出せば学生を惹き付けられるのか…」と頭を悩ませるでしょう。
学生が見ているのは「人柄と雰囲気」
人事担当者様が会社説明会において、学生の言動を観察して貴社への志望度を探っているのと同じように、学生も人事担当者様の話し方や表情から、人柄や会社の雰囲気を感じ取っています。
説明会が「説明するだけ」で終わってしまうと、学生はリアルな人柄や普段の社風を知る機会を得られません。
結果として、印象に残らず惹きつけにつながらないのは明らかです。
そのため、私たちMOCHICA運営部は、人事担当者様に対し「説明会と座談会の同時開催」を提案しています。
開催までの準備と進め方
学生にとって「説明会」「座談会」は、企業の雰囲気を感じ取る第一歩になります。これからどのような仕事をして、働くのかというイメージを持てるかどうかがポイントになります。
1.開催時間の設計
説明会と座談会を同時にやる、と考えたとき「どっちにどれくらいの時間を割り振るべきか…」と悩むと思います。
上述のとおり「説明」ばかりでは、学生が飽きてしまい惹き付けはできません。
かと言って、座談会に時間を多く割り振ると、貴社のビジネスモデルや仕事内容を理解していない学生が続出し、これもまた「満足」とはほど遠い結果になりがちです。
結論から言うと私たちMOCHICA運営部では、90分構成(説明45分+座談会45分)をおすすめしています。
こちらは、大学の1コマ授業をもとに構成された内容です。
1コマの90分と同じ時間間隔なので、集中力も持続しやすく、内容のバランスも良いです。
2.開催形式は基本的に「ハイブリッド」で
コロナ禍を経て、今では「説明会は対面で」という企業が増えています。一方で地方学生や多忙な学生にとってはオンラインの機会がありがたいのも事実。
そのため「対面とオンラインのハイブリッド開催」は、もはや採用のスタンダードになりつつあります。
実際、弊社で学生の就職支援サービスを利用している学生に話しを聞くと「会社へ行ったほうが雰囲気をつかみやすい」と答える学生は少なくありません。
人事担当者様も、新入社員になる可能性のある、早い段階で学生を自分の目で見れたほうが安心でしょう。
社会全体で、対面開催に戻そうとする動きが活発な中、ではありますが、基本的に対面とオンラインを併用する“ハイブリッド開催” がおすすめです。
人事担当者様は、さまざまなセミナーで耳にタコができるほど聞かされていると思われますが、オンライン開催には「地方の優秀な学生にアプローチできる」とのメリットがあります。
3.プログラムの立案
実施方法を決めたら、次は当日の内容を考えましょう。
企業側として、伝えたい情報はもりたくさんかと思いますが、学生が最も知りたいのは「入社後のリアルな姿」です。
ご担当者様側が発言する「説明の時間」は、5分くらい後ろ倒しになっても問題ありませんが、目安として20分程度が適切です。以下、その内容にすべきか理由を交えながら書いていきますので、プログラムを考えるときの参考にしてみてください。
(1)説明会のプログラム
まずは説明会から。
①代表挨拶(3分程度)
HPにある情報の繰り返しではなく、今の想いやエピソードを交えることが大事です。インターンシップや説明会に参加する学生の多くは、HPやナビサイトで貴社の情報をある程度調べている確率が高いです。
そのため、代表挨拶は3分で十分です。
②事業概要(3分程度)
こちらも、上述と同様の理由で長い説明は不要です。
時間の目安としても3分。会社のホームページなどを基礎資料にし、口頭で補足しながら進める程度で構いません。
③オフィス紹介(3~5分程度)
事業概要の説明後、実際の会議室や休憩スペースを移すことは学生に安心感を与えます。VTR等で職員玄関や廊下、ロビー、面接会場(会議室)、休憩スペースを見せることで学生としては選考や入社後のイメージを持ちやすくなります。説明の時に「学生さんには、ここ(会議室など)で面接を受けていただきます」など、シーンに応じた補足があるとなお良しですね。
動画の長さにもよりますが、良いテンポで進めるには長くても5分以内がおすすめです。
④社員インタビュー(2~3分程度)
オフィスの様子を移す動画では伝えきれない人柄の補足になります。入社2~6年目の社員に「志望動機」「入社前後のギャップ」等を話していただくと効果的です。
⑤質疑応答
企業側が「分かりやすく伝えようとさまざまな準備をしても、それで確実に伝わるとは限りません。
説明会のプログラムが終ったあとにも質疑応答を設けると思われます。
ですが、学生の理解度を深めるため、会社紹介が終った直後にも質疑応答があると親切です。
ただし、学生が緊張しているため質問が出ない可能性があります。
そのときには、学生同士が話しやすいよう、人事担当者から「今お見せした情報以外で知りたことはありますか?」「ビデオを見てどうでしたか?」など、質問をうながしましょう。
学生の多くは大学などで「こういう質問をすると印象がわるくなる」といったセミナーを受けて説明会に臨んでいます。そういった”誤情報”が原因で質問が質問が出ない可能性も考えられます。
その可能性を考慮して質疑応答の前に、人事担当者様から「ここで、どんな質問をしても、選考には影響しない」とハッキリ言ってあげてください。たった一言ですが、これがあるかないかで学生はリラックスでき、質問のハードルが下がり、質疑応答が活発になります。
学生から多く質問が出ると想定して、質疑応答は5〜10分程度確保しましょう。ひとしきり質問が出尽くしたならば、予定時間に達してなくても座談会へ移っていただいて構いません。
(2)座談会のプログラム
続いて座談会になります。
①参加人数の配分
座談会の目的は、人事担当者様が説明会で伝えきれなかった社内の情報、
学生が説明会の質疑応答で聞きそびれた質問に答え、自社についてさらに理解を深めてもらうこと。
また、学生と貴社の社員様が”顔見知り”になることにあります。
説明会と同じように「人事担当者様4〜5名」対「 大勢の学生」との構図でやってしまっては、学生1人あたりの発言時間が減ってしまい、上述の目的は果たせません。
これでは本末転倒です。そのような事態を避けるため、事前に会議室を10いくつか押さえておいて、学生が最大5名になるよう、グループを作り会議室へ移動を促してください。
先ほど「説明の時間は20分を目安にすると良い」と書いたのは移動時間を考慮してのことでした。
とは言え、会場でグループ分けをしようとすると、それだけで10分以上かかってしまいます。
このため、説明会・座談会の案内の中に「A-1室」など部屋番号を明記し、順番に移動を促すと、学生を必要以上に待たせず、スムーズに座談会へ移行できます。
WEB形式で開催する場合は、移動時間がないので、zoomなど貴社が使用したツールのグループ分け機能を使って速やかに、座談会へ移行しましょう。
②座談会でモデレーターを務める社員の選び方
説明会と同じ内容を話しても、説明会と代わり映えせず学生はすぐ飽きてしまい、肝心の惹き付けにはつながません。学生を飽きさせないため、私たちMOCHCA運営部では「入社3〜4年目の社員にモデレーターを任せるのが良い」とお伝えしています。
入社3〜4年目の社員は、入社5〜6年目の中堅社員様に比べると、キャリアビジョンや業務への理解があいまいな場合もあるかとれますが、学生は、就職活動からあまり時間が経っていないため、より学生に近い感覚で話せます。
先ほど、説明会のとき「志望動機、今の会社を目指したきっかけ」や「入社前のイメージと、実際に入社した後の印象」を話してもらうのが有効、と、書きましたが、同じ質問を入社3〜4年目の社員様に投げかけると、中堅社員様とは違った答え、あるいは就職活動へのあありますドバイスを聞けるでしょう。
こうした人材配置をすると、学生にとっては「座談会」でありながら、貴社にとっては、座談会が「若手社員様を育てる場」になります。
中堅社員様としては不安に感じる部分もあるかと思われますがひんぱんにくちを挟んでしまっては、若手社員様の成長につながりません。口を出すのはモデレーターを務める若手社員様の事業や業務への理解が間違っているとき。
説明に不足があるとき。あるいは、緊張で若手社員様の進行が止まってしまったときだけに留めましょう。
説明会終了後の接点づくり
学生を惹き付けるためには、説明会終了後のフォローが大事です。
人事担当者様に伺いたいのですが、「A社」から商談を受けたとき『いい話を聞けたと思った2〜3日後、「B社」から商談をうけ『B社もなかなかいい提案をしてきた』と思った経験はありませんか。
同じような会社が2つあって、こちらの要望をある程度聞いてくれると、人は先方の前では、無意識のうちに「得する話しを聞いた」と感じてしまうものです。ところが、商談が終わり渡された資料を見ながらA社とB社の違いを考えていると不思議と違いが分からなくなり”迷い”を感じ始めます。
それと同じで説明会終了後、時間が経つにつれて「どこの会社を受けるのが自分にとって正解なのか…」と迷いを感じている学生は少なくありません。
1.ツールの選び方
学生と関係性を継続するとき、まず気をつけていただきたいのが連絡ツールの選び方です。
、東京工科大学が実施した調査によると、2015年以降LINEの利用率が90%を超えています。
数多くの企業様や商業施設が相次いでLINEアカウントを開設した結果、学生にとって「貴社とLINEでつながること」に抵抗を感じる学生は少なくなってきています。
ただしLINEはつながるのも簡単ですが、ブロックされるのもあっという間です。
少しでも信頼できないと感じれば、学生は貴社のアカウントをブロックし競合他社へいきます。
また、「就職活動にLINEを使いたくない」と考える学生も一定数います。
そういった学生の意向を無視してしまっては、関係の継続は見込めず選考までに辞退されるのが関の山です。
着実に信頼関係を築くため、「今後も連絡して良いか」「良い場合には何のツールを使うか」。
そして、「何時ごろにメッセージを送れば見やすいか」。
この3点を当該学生と話し合った上でフォローを始めてください。
2.コミュニケーションを取り始めるタイミング
「フォローをしっかりしたほうが良い」と分かっていても、人事担当者様が悩むのは「いつからコミュニケーションを取るのがいちばん効果的か」だと思います。
結論から言うと、これは学生と接点をもった直後から始めるべきです。
上述のとおり、学生は貴社の説明会で「良い話を聞けた」と思っても、別の会社で話しを聞けば「こっちも良いな」と悩み始めます。これは、学生が優柔不断なわけでもなく、人事担当者様に非があるわけでもありません。
彼(彼女)にとって”新卒の就職先”は、1社だけです。最初にどんな会社に入り、何の仕事をするかでビジネスパーソンとして身につく能力とキャリアプランが決まります。
だからこそ、多くの学生は入社先を悩むのです。
ビジネスパーソンの先輩として、彼(彼女)らの不安に寄り添うつもりで、説明会の直後から学生とコミュニケーションを取り始めてください。地道ですが、その繰り返しが信頼関係をつくり、選考や内々定通知後の辞退につながります。具体的なコミュニケーションのとり方については、以下の記事にまとめていますので参考にしてみてください。
まとめ
就職活動中、学生の気持ちは人事担当者様が想像される以上に揺れ動きやすいものです。
就職活動を行っているのは、物心ついたときにはスマートフォンが生活の中にあるのが当たり前な”デジタルネイティブ世代”。
そんな彼(彼女)らにとって、貴社の情報を調べるのは難しくありません。
学生が求めるのは、「入社後の仕事内容」「飾らない社内の様子」など社員様しか知り得ない情報です。それを伝えるために開催形式は対面であれWEBであれ「説明会と座談会をセットで実施する」という方法が有効です。
それが”惹き付けへの第一歩”となります。
その上で、説明会終了後も学生1人ひとりと定期的にコミュニケーションをとり、人事担当者様が、学生にとって「悩みを打ち明けやすい存在になることこそが、選考辞退、内々定通知後の辞退抑止につながります。
弊社で提供しておりますMOCHICAは、人事担当者様と学生の接点を切れにくくするため、連絡方法を「メール」または「LINE」から、学生の希望に応じて選べるようにしました。
加えて、人事担当者様が気になるのは「採用業務に係る工数」だと思います。
私たち、MOCHICA運営部では人事担当者様が無理なく、かつ、失敗なく運用できるように「貴社に専任のスタッフ」をつけるという方法で運営しております。
ご契約後は、専任のスタッフがシステムの導入や、メッセージの作成をサポートいたしますので、万が一、人事担当者様が私用業務に割ける時間がないときでも安定して運用でき、そこにかかる工数の大幅な削減が可能です。
「LINE採用の始め方」に関する資料を無料配布中
企業への連絡の際、「失礼があったら評価に影響する」と考え、電話やメールの言い回しに悩む学生は少なくありません。採用担当者とのコミュニケーションは、学生にとって非常に気を使う行為の1つです。
採用担当者様の多くは入社後を見据え「ビジネスマナーの有無」を重視されるかと思います。
もちろん、「挨拶をする」「TPOに応じたことばを使う」といったマナーは必須ですが、そこにこだわり過ぎると、学生が萎縮してコミュニケーションが滞りがちです。
そのまま面接に臨んでも、学生からは形式的な答えしか返ってこないでしょう。
学生の本音を聞くためには、「採用担当者との、コミュニケーションのハードルを下げる」作業が不可欠です。
若い世代の利用率が高いLINEを連絡手段として活用するほか、選考にも取り入れた方が、学生と関係を構築しやすくなります。
下記フォームから、「LINE採用のメリット」や「LINE運用の注意点」をまとめた資料を、無料でダウンロードいただけます。LINEの導入を検討されている企業様や、学生とのコミュニケーションに課題を感じている企業様は是非お申し込みください。
以下の資料をご覧いただけます